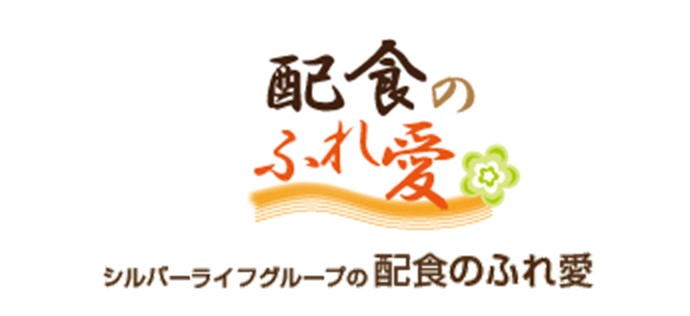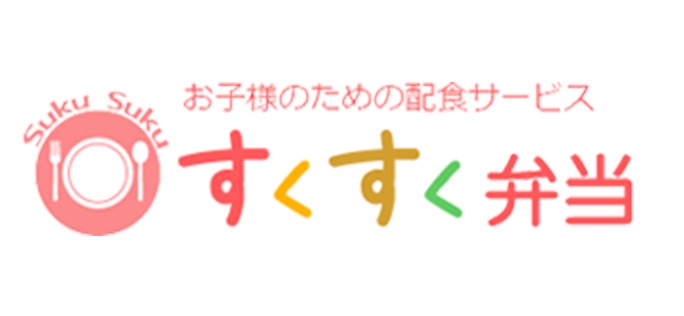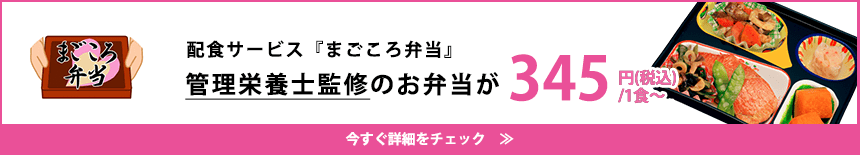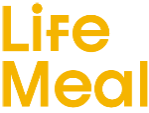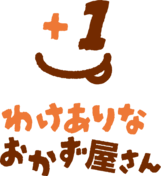インフルエンザを予防しよう!バランスのいい食事で!
作成日:2021年1月7日

毎年冬になると、流行するインフルエンザウイルスですが、インフルエンザにかかると高熱が出たり、家族に移してしまったりと大変な思いをしてしまいます。予防しようとワクチンを接種したのに、かかってしまったという人もいるのではないでしょうか。今回は、インフルエンザについてとその予防について詳しくお話していきます。
目次
インフルエンザについて
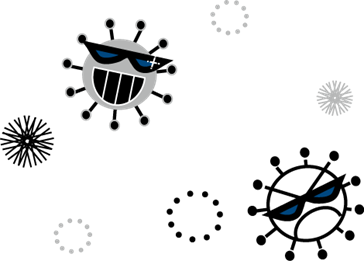
インフルエンザとは、地球の北半球では毎年1~2月ごろに流行のピークを迎えるインフルエンザウイルスによる気道感染症のことです。日本では、寒くなってくる11月下旬から12月にかけて増え始めて、1月2月でピークを迎え、あたたかくなってくる春ごろには徐々に減少傾向となります。
インフルエンザウイルスにはA、B、C型があり、世界的に流行するのはA型とB型と言われています。特にA型のインフルエンザウイルスは、ウイルス表面に突き出たたんぱく質の種類によって144種類にも分類されます。この1つ1つによって、身体の中にできる抗体(感染した後にできる免疫)が異なるため、1度A型のインフルエンザウイルスにかかったことがあったとしても、違う種類のA型インフルエンザウイルスにかかってしまうということがあります。
インフルエンザウイルスに感染してから、症状が出るまでの期間(潜伏期間)は1~5日と言われており、感染したからと言って必ずしも症状が出現するというわけではありません。潜伏期間中や、症状が出現していないけどウイルスに感染している状態でも、他人へとうつす可能性があるとされています。
インフルエンザと普通の風邪の違い

一般的に風邪と言われる症状はさまざまなウイルスによって引き起こされる、のどの痛みやくしゃみ、咳などの気道の炎症によっておこる症状をさします。重症化することはあまりなく、数日たてば症状が軽快していくことがほとんどです。
一方、インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって症状が引き起こされます。インフルエンザは、普通の風邪でおこるようなのどの痛みやくしゃみ、咳に加えて、38℃以上の急な高熱、関節痛、頭痛、全身のだるさなど、全身に症状が出現します。小さい子どもがかかると、脳症(意識障害やけいれん、異常言動などを引き起こす脳の病気)を発症することがあります。
また、高齢者がインフルエンザにかかると肺炎などを引き起こして重症化することがあります。このようにインフルエンザは、普通のウイルスによる風邪よりも全身症状が強く、重症化しやすいという特徴があります。通常は1週間程度で回復すると言われています。
インフルエンザが重症化しやすい条件としては、上記で述べたような5歳未満の子どもや65歳以上の高齢者に加えて、妊娠中の方や肥満の方、様々な持病(喘息や慢性肺疾患などの呼吸器系の疾患、心不全などの循環器疾患、肝臓や腎臓の疾患、糖尿病など)を抱えている方と言われています。
インフルエンザの予防

1) 予防接種
インフルエンザの予防ワクチンを接種することによって、インフルエンザの発症のリスクを減らすだけではなく、発症後の重症化のリスクを減らすこともできると言われています。摂取したワクチンは、予防効果を発現するまでに1~2週間かかるとされており、爆発的な流行を迎える12月~3月の間にワクチンの効果を発揮するためには、11月末まで、遅くとも12月中旬までにはワクチン接種を終えておくことが理想的です。
しかし、インフルエンザの予防接種を受けたとしても必ずしも発症を予防できるわけではありません。最初に述べた通り、流行するA型インフルエンザには144種類もの種類があり、摂取したワクチンの型と、その年に流行するインフルエンザの型が一致するとは限りません。そのため、インフルエンザのワクチンを接種したとしてもかかってしまうということもあり得ます。ワクチンを接種したからと安心するのではなく、自分でできる予防対策を行う必要があります。
2) 手洗い
インフルエンザは飛沫感染によって感染すると言われています。飛沫感染とは、感染した人が咳やくしゃみをしたときに飛び散るウイルスを吸い込んだり、ウイルスがついた手で口や鼻を触ることによって感染します。厚生労働省は、外出先からの帰宅時、咳やくしゃみ、鼻をかんだとき、食事の前後、病気の人のケアをしたとき、外にあるものを触った時の5つのタイミングでこまめに手洗いを行うよう推奨しています。
また、手洗いなしの場合と比較して、流水で15秒手洗いするだけでも手に残るウイルス量は約1%まで減らせるということが分かっています。ハンドソープを使用して流水ですすぐ手洗いをした場合には、流水で手洗いする方法よりもさらにウイルス量を減らすことができると言われています。
風邪予防の際には、手洗いとセットでうがいを推奨されていますが、実はインフルエンザの予防に関してはうがいの有効性は科学的に実証されていません。インフルエンザウイルスが、口や鼻から侵入しのどの粘膜や気管支の細胞に付着した場合、細胞の中へ数分~20分程度という速さで侵入してしまうと言われています。そのため、うがいをしたところで、ウイルスの侵入を防ぐことは難しいと考えられているためです。
インフルエンザ以外のウイルス感染や細菌感染にはうがいは予防効果があるとされているため、手洗いのタイミングでうがいをするのはインフルエンザ以外の感染症予防としては大切であるといえます。
3) 咳エチケットを守る
咳エチケットとは、咳やくしゃみが出そうなときには、他人に向けてしないことや、とっさの時には、ティッシュや腕の内側で口や鼻を覆うなどして、他人へのウイルスの飛散を予防することを言います。咳やくしゃみのしぶきは目には見えなくても、1~2mは飛散すると言われています。そのため、咳やくしゃみが出そうなときには咳エチケットを守って他の人へウイルスを広めないようにしましょう。
また、咳やくしゃみが出そうなときに手のひらで口元を覆ってしまうと、手のひらにウイルスが付着してしまい、そのウイルスが付着した手でさまざまなものを触るとそこからウイルスを広めてしまいます。そのため、ティッシュや腕の内側で口元を覆う必要があります。咳やくしゃみをした後のティッシュや鼻水を処理した際に使用したティッシュは、すぐに密閉したビニール袋などに入れて処分するようにしましょう。
また、マスクを正しく装着することもウイルスを広めるのを予防するのに有効とされています。マスクと顔の間に隙間ができないように、装着する際には鼻の部分やあごの部分がしっかりと密着していることを確認しましょう。
4) 適切な湿度、室温を保つ
冬は暖房を使用することや気候的にも乾燥しがちです。乾燥した環境だとウイルスがホコリと一緒に舞い上がって人に感染しやすくなってしまいます。インフルエンザウイルスは湿度の高い環境に弱く、湿度を一定以上に長時間保つことで増殖力や感染力を弱めることができると言われています。
また、インフルエンザウイルスは吸い込んで、鼻やのど、気管支の粘膜に付着しそれが身体の中に取り込まれることによって感染します。本来であれば、付着したウイルスなどは粘膜にある絨毛(じゅうもう)という細かい毛が外へ排出しようとする動きが働きますが、乾燥した環境であると、この絨毛の運動が低下してしまいます。そのため、鼻やのど、気管支に付着したウイルスが外へ排出されにくくなり、インフルエンザに感染しやすくなってしまいます。
インフルエンザが流行する冬は、意識的に加湿器などを利用して加湿を行い、湿度50~60%程度を保つように心がけるようにしましょう。加湿器がない場合には、濡らしたタオルを室内に干しておくだけでも加湿されるため試してみましょう。
インフルエンザウイルスは、低温環境を好むとされているため、室温は18~20℃を保つように環境を整えましょう。ただし、室内を閉め切ると感染のリスクが高まるので、1~2時間に1度は換気をして室内の空気の入れ替えをするようにしましょう。
5) 人込みへの外出を避ける
インフルエンザは、人を介して感染します。そのため、流行時期には、なるべく人混みを避けることも感染予防のためには大切です。外出は必要最低限にとどめて、外出の際にはマスクを着用したり、外出から帰った際には手洗いを行ったりすることで、感染予防することができます。
6) 規則正しい生活、バランスのよい食事を心がける。
インフルエンザウイルスが、もしも身体の中に侵入した場合でも、身体の免疫によって発症する前に退治することもできます。免疫力を高めるためには、まずは十分な睡眠をとったり生活リズムを整えることが重要です。
そして、バランスのよい食事を摂取して免疫力を高めましょう。特に免疫力を高めると言われている栄養素は、ビタミンやたんぱく質、発酵食品などです。
① ビタミンA
ビタミンAには、ウイルスが侵入してくる鼻やのど、気管支の粘膜を丈夫にする働きがあると言われています。ビタミンAはにんじんやほうれん草、ブロッコリーなどの緑黄色野菜や、レバーやうなぎなどに多く含まれています。
② ビタミンC
ビタミンCにも、皮膚や粘膜を丈夫にする働きやウイルスの増殖を防ぐ働きがあると言われています。他にも、免疫力を下げるとされている活性酵素を押さえる働きもあると言われています。ビタミンCは、緑黄色野菜や果物などに多く含まれています。
③ ビタミンE
ビタミンEは、血行をよくする働きがあり鼻やのど、気管支の粘膜を健康的に保つ効果があるとされています。またビタミンCと同様に活性酵素を抑える効果があるため、免疫力向上に効果的と言えます。ビタミンEは魚介類や野菜、ナッツ類に多く含まれています。
④ ビタミンD
ビタミンDは、免疫機能を高める働きがあるとされており、ビタミンDを摂取したらインフルエンザにかかりにくくなったとする研究結果も報告されています。ビタミンDは乳製品や魚介類、卵などに多く含まれています。
⑤ たんぱく質
私たちの身体は、ほとんどがたんぱく質からできています。侵入したインフルエンザウイルスとたたかう免疫細胞もたんぱく質からつくられています。肉や魚、卵、大豆製品などには良質なたんぱく質が豊富に含まれているため、これらを摂取することによって身体の免疫力を上げることができます。
⑥ 発酵食品
ヨーグルトやみそ、納豆などの発酵食品には、腸内環境を整える働きがあります。免疫細胞は腸の中に多く存在していると言われており、腸内環境を整えることによって免疫細胞が活性化されるとされています。
これらの感染予防によいとされている食材だけを食べればよいというわけではなく、さまざまな食材をバランスよく摂取することで効率的に栄養が吸収されたり、効果を発現させやすくなったりします。たくさんの食材をバランスよく摂取することが大切です。
インフルエンザ予防のまとめ

インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされ、日本では12月~3月頃に流行の時期を迎えます。小さい子どもや高齢者は重症になることもあり、一般の風邪よりも警戒が必要な感染症の1つです。
インフルエンザを予防するためには、予防接種を受けたり、手洗いや咳エチケットを守るなどの予防行動が重要になってきます。それと同時に大切であるのが、そもそもの自分の免疫力を高めることです。例え、ウイルスが身体の中に侵入してきたとしても免疫力が高ければ発症させずにウイルスを退治することができます。
身体の免疫力を高めるためには、規則正しい生活を送ったりバランスの良い食事を摂取することが大切です。免疫力を高めるといわれている食材を意識的に摂取し、それだけに偏るのではなくさまざまな食材をバランスよく食べることを心がけましょう。
宅配サービスのまごころ弁当では、毎日日替わりでさまざまな食材を使用した栄養バランスのよいお弁当を食べていただけます。人込みで買い物をして、ウイルスへの感染が心配な方にも、買い出しに行かずに免疫力を高める食事を食べていただけるのでおすすめです。寒い冬に流行のピークを迎えるインフルエンザにかからないために、手洗いやマスク着用など、自分でできる感染予防行動だけでなく、まごころ弁当を活用して身体の内側から免疫力を高めていきましょう。
 まごころ弁当
まごころ弁当  配食のふれ愛
配食のふれ愛  宅食ライフ
宅食ライフ  すくすく弁当
すくすく弁当  まごころケア食
まごころケア食  ライフミール
ライフミール  わけありなおかず屋さん
わけありなおかず屋さん  運営会社
運営会社  こだわりシェフ
こだわりシェフ おてがるシェフ
おてがるシェフ ラクゴハン
ラクゴハン ラクミール
ラクミール まごころ食材
まごころ食材 楽らく弁当
楽らく弁当
 HOME
HOME まごころ弁当とは
まごころ弁当とは 店舗検索
店舗検索 注文方法
注文方法 コラム
コラム お問い合わせ
お問い合わせ