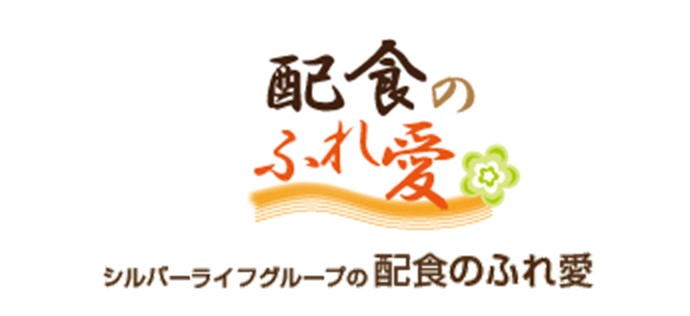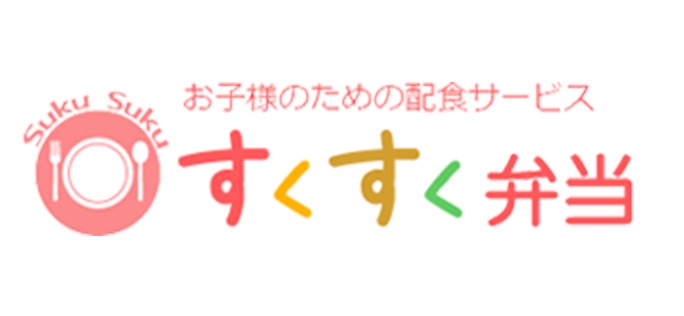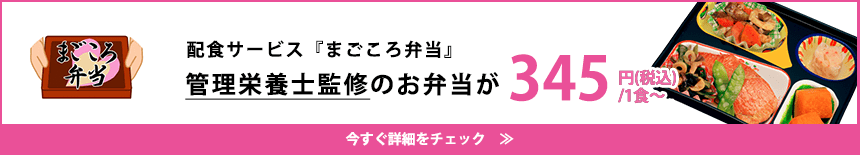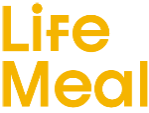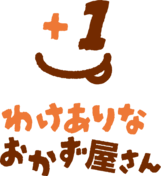夏越の祓とは?行事の由来やこの時期食べる水無月とは?
作成日:2022年5月28日

6月の終わりに、草をまとめて作った大きな輪をくぐる神事があるのをご存じですか?
夏越の祓と呼ばれるこの神事、そして、この頃に京都で食べられる水無月と呼ばれる和菓子について、その由来やレシピをご紹介します。
目次
夏越しの祓の起原とは?
夏越(なごし)の祓(はらえ)とは、6月30日、つまり、6月の晦(みそか=末)日に行われている行事のことで、茅輪神事(ちのわしんじ)または、水無月祓(みなづきはらえ)とも呼ばれています。
夏越の祓は、1月からの半年間、私たちの身に降りかかってきた穢れを祓い、残り半年間の無病息災を祈る行事です。
では、この神事はどのようにして産まれたのでしょうか?
夏越の祓の歴史は古く、日本書紀の頃、西暦180年頃までさかのぼると言われています。
奈良時代に執筆された『備後風土記』という書物によると、素戔嗚尊は旅の途中、宿を求めて数軒の家をたずねます。
そのとき、裕福な巨旦将来(こたんしょうらい)という人物は、宿として部屋を貸すことを断ります。
その兄である蘇民将来(そみんしょうらい)は貧しいにもかかわらず、自宅を宿として提供し、粗末な食事、粟柄を敷き詰めて作った床ではあったものの、精一杯もてなしたということです。
数年後、蘇民将来のもとを再び訪れた素戔嗚尊は蘇民将来の子や孫に、「茅の茎で作った茅の輪を腰につけておくと疫病から免れる」と言われました。
その夜の内に近辺で疫病が流行り、茅の輪を身に着けていた蘇民将来の家族以外は死に絶えてしまいました。
素戔嗚尊は、「今後、蘇民将来の子孫だ、といって茅の輪を腰につけておけば、疫病が流行ったとしても、助かることができるだろう」といって立ち去りました。
それ以来、茅の輪は疫病除け、厄除けの力があるとされ、6月晦日に行われる夏越しの祓の神事へと発展していったということです。
また、この故事にちなみ、京都府の八坂神社で行われる有名な祇園祭は、蘇民所来子孫の札と粟餅を配り、夏越の祓が行われてひと月に及ぶ祭の幕を閉じます。
同様に、島根県出雲地方、三重県志摩地方をはじめとする地域では、「蘇民将来子孫」という札を厄除けとして家の門に下げる習わしがあります。
夏越の祓 その行事とは
神事を執り行う神社を訪ねた時は、手水をとり、身を清めます。
神職の祝辞のあと、神職を先頭に参拝者が列となり、神社の鳥居やその付近に設置された茅の輪を、一周目「水無月の夏越の祓する人は、千歳の命延(の)ぶというなり・思ふ事」『拾遺和歌集・読み人しらず』、二周目「思ふことみなつきねとて麻の葉を きりにきりても祓へつるかな」『後拾遺集・紫式部』、三周目「蘇民将来」と唱えながら、8の字を描くように左回り→右回り→左回りの順で、3回続けてくぐります。
このことで、新年から6月晦日までの半年間の厄や穢れを祓い、残り半年間の無病息災を祈るのです。
くぐった茅の輪には、行事に参加した人の厄が移っているとされるため、抜いて持ち帰ることはおすすめできませんが、神社によっては小さな茅の輪の授与があるところもありますので、そちらをいただいて帰るのもよいですね。
また、地方によっては厄払いのために作られた和紙の形代(かたしろ)又は人形(ひとがた)が用意されています。
年齢や名前を記入した人型に穢れを託すように、頭の先からつま先までをなぞり、息を吹きかけます。
そのあと、元の和紙に包み、神職に手渡し、お焚き上げにしたり、川に流したりします。
夏越の祓の行事は室町時代、応仁の乱をきっかけに中断され、全国的には行われなくなっている行事でもありますが、明治天皇の布告により、明治5年頃に再び執り行われるようになりました。
夏越の祓にいただく水無月とは
長らく行われていなかった神事ではありますが、京都では夏越の祓の頃にいただく、水無月(みなづき)というお菓子があります。
その名の通り、6月の夏越の祓の頃にいただくもので、外郎(ういろう)の上に小豆を炊いて作る甘納豆がちりばめられ、三角形に形どられた和菓子です。
水無月が三角形をしている理由
旧暦の6月、水無月は、今でいう梅雨ではなく、梅雨が明けて初夏を迎える頃を指しています。
冷凍庫やエアコンがない時代の人々は、氷室(ひむろ)と呼ばれる場所に冬の間に保管しておいた大きな氷を砕き、暑気払いとして口にしていました。
大きな塊から砕いた氷は、現代のように製氷皿で作るのとは違い、一つ一つ違う三角形に近い形をしています。水無月の三角形は、この氷の形を模しています。
小豆がちりばめられている理由、小豆の栄養とは?
日本では、古来より赤いものには霊力が宿り、魔除けの力があると信じられていました。
そのため、現代でも祝い事で食べられる赤飯、また、小正月にいただく小豆粥など、祭事の食卓には小豆がよく用いられています。
中医薬膳学では、小豆はむくみを解消し、体にこもった熱を発散したり、かゆみを伴う発疹を鎮めたりする働き、また、解毒作用があるとされています。
食物繊維
食物繊維には、水溶性、不溶性の2種類が知られています。
小豆には不溶性食物繊維が多く含まれており、消化されることなく腸まで届き、便のカサを増やして便秘解消に役立ちます。
レジスタントスターチ
小豆に含まれるでんぷん質は茹でるとレジスタントスターチという難消化性でんぷんに変化します。
レジスタントスターチは、でんぷん質でありながら消化されにくく、不溶性食物繊維同様に便の量を増やし、便秘を解消してくれるほか、水溶性食物繊維と同様の働き、腸内細菌のえさとなり、腸内環境を整える働きもあります。
カリウム
カリウムは私たちがとりすぎた塩分を体外へと排泄し、血圧の上昇を抑えたり、むくみを解消したりする働きがあります。
鉄
体内に含まれる鉄分の約65%は血液中のヘモグロビンに含まれ、体の隅々まで酸素を運ぶ役割を果たしています。
不足すると鉄欠乏性貧血を引き起こします。
亜鉛
亜鉛は私たちが摂取したたんぱく質の再合成、DNAの合成にかかわる酵素の材料として働きます。
そのため、亜鉛が不足すると細胞の再生が上手く行われなくなり、特に味を感じる味蕾という舌の上の細胞の再生が上手くいかなくなると、味覚障害を引き起こすことが知られています。
銅
銅は私たちの体内では赤血球の中のヘモグロビンに鉄を合成する役割を果たしています。
そのため、鉄分を取っていても銅が不足すると、ヘモグロビンの合成がうまくいかず、赤血球が小さくなり、貧血状態に陥ります。
また、不足すると毛髪の色素が抜けたり、骨がもろくなったりすることがあります。
ビタミンB1
ビタミンB1は糖質の代謝を促し、素早くエネルギーを作り出すことから疲労回復効果が期待できます。
糖質が唯一の栄養素と言われる脳の働きを正常に保ち、集中力や記憶力を維持したり、中枢神経や末梢神経の働きを高めたりする働きがあります。
ナイアシン
ナイアシンは私たちが摂取した糖質や脂質をエネルギーに変える働きがあります。
また、皮膚や粘膜を健康に保ったり、肝臓でアルコールの分解を助け、二日酔いを予防したりします。
やわらかもちもち水無月の作り方

京都を中心に食べられている水無月、最近は関東の和菓子屋さんでも見かけられるということですが、まだまだほかの地方では一般的ではないかもしれませんね。
水無月はもちもちとした外郎(ういろう)の上に、甘納豆が乗っているとてもおいしい和菓子です。
材料も手軽に手に入るものばかりですので、ぜひ手作りして楽しんでくださいね。
基本の水無月
【材料】
・白玉粉…50g
・上新粉…150g
・砂糖(上白糖)…60g
・水…300cc
・甘納豆…200g程度

【作り方】
①ボウルに白玉粉、水を入れ、よく混ぜて塊をほぐしておきます。

②①に砂糖、上新粉を加え、さらに混ぜます。
③②を茶こしなどで濾し、50cc程度取り分け、残りを流し缶や電子レンジに入れられる耐熱容器に流します。

④蒸気の上がった蒸し器に入れ、中心まで火が通るまで蒸すか、ふんわりとラップをかけ、600Wの電子レンジで3~4分程度加熱し、火を通します。必要に応じて再度加熱し、中心まで火を通します。

⑤火が通ったら取り出し、表面の水分をキッチンペーパーなどで優しくふき取り、③で取り分けておいた50ccの生地を表面に流します。

さらに、甘納豆を表面に広げるように並べ、全体に火が通るように蒸し器に入れて蒸すか、電子レンジ600Wで3~4分蒸します。

⑥しっかりと荒熱を取り、型から取り出して三角形に切り分けます。この時ベタベタとくっつきやすいので、包丁は濡らして使用し、一度切るごとについた生地を洗い流し、再び濡らして使用するときれいに切ることができます。

アレンジメニュー
黒糖の水無月
上白糖の分量を黒糖に置き換えて作ります。
塊の黒糖の場合はあらかじめ包丁で細かく切っておき、作り方①で白玉粉と共に水に加え、ダマが残らないようによく混ぜ溶かします。
抹茶の水無月
水無月の季節はちょうど2番茶の摘み取りの時期に当たります。
抹茶に含まれる茶カテキンは、効率よく脂肪を燃焼させたり、肌のシミ、シワを防いだりする働きがあります。
抹茶パウダー…小さじ1杯程度
抹茶パウダーを上新粉に合わせ、ダマにならないように振るっておき、作り方②で加えます。
ニッキの水無月
水無月は、抹茶以外にもニッキ(シナモン)の香りもよく合います。
シナモンには血行を促進し、冷えを解消したり、肩こりや腰痛を解消したりする働きがあります。
シナモンパウダー…小さじ1/2程度
シナモンパウダーを上新粉に合わせ、ダマにならないように振るっておき、作り方②で加えます。
まとめ
今回は、6月晦日に行われる夏越の祓の行事や食べ物について、ご紹介しました。
一旦途切れてしまった行事のため、地方によっては何の行事も行われないところもあるかもしれません。
夏越しの祓はちょうど一年の折り返し地点、梅雨が明けて暑い夏が訪れる頃です。
祭ごとはなくても、半年を振り返り、暑い夏に備えて体調の悪いところを治療したり、食生活を見直し、軽い運動を取り入れたりするなどしてみる機会にしてみてくださいね。
古の人々は冬の間に切り出した氷を氷室から取り出し、口にして暑い夏を凌いだということですが、現代の私たちは栄養バランスが整った食事をとることで体調を整え、季節の変化に対応することができます。
ですが、毎日の食事を、家族一人一人の体調に合わせて栄養バランスが整ったものにするのは難しいものです。
そんな時におススメしたいのが、まごころ弁当のお弁当です。
まごころ弁当のお弁当は、健康に自信がある方にももちろん、ダイエットや生活習慣病を気にしておられる方向けのカロリー調整食、持病による食事制限がある方にもお召し上がりいただけるたんぱく調整食や咀嚼・嚥下の不安がある方向けの刻み食やムース食など、バリエーションも豊富な選択肢の中からご家族の状態にあったひと品を選んでいただくことができます。
今なら無料試食キャンペーンを実施中です。この機会にぜひお試しくださいね。
 まごころ弁当
まごころ弁当  配食のふれ愛
配食のふれ愛  宅食ライフ
宅食ライフ  すくすく弁当
すくすく弁当  まごころケア食
まごころケア食  ライフミール
ライフミール  わけありなおかず屋さん
わけありなおかず屋さん  運営会社
運営会社  こだわりシェフ
こだわりシェフ おてがるシェフ
おてがるシェフ ラクゴハン
ラクゴハン ラクミール
ラクミール まごころ食材
まごころ食材 楽らく弁当
楽らく弁当
 HOME
HOME まごころ弁当とは
まごころ弁当とは 店舗検索
店舗検索 注文方法
注文方法 コラム
コラム お問い合わせ
お問い合わせ