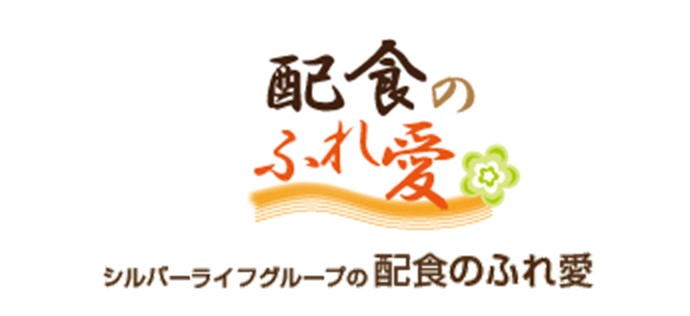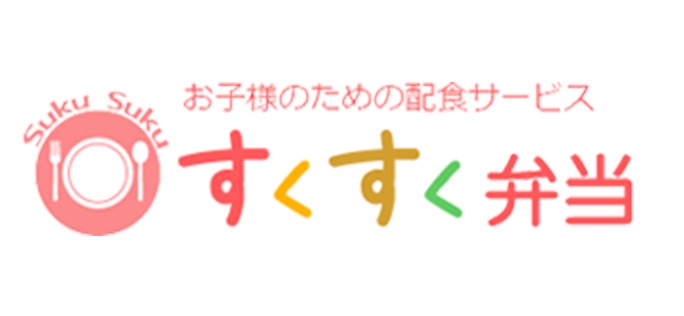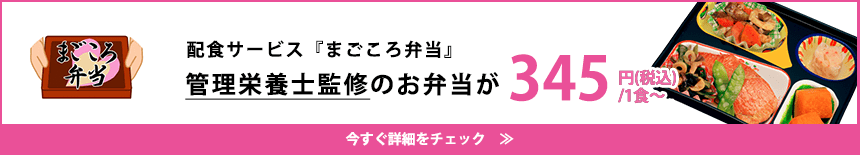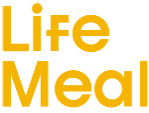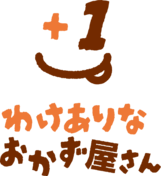高齢者の入浴介助のコツとは。注意点を踏まえて解説
作成日:2022年8月29日

入浴が楽しみという高齢者の方は多いのですが、入浴には病気やケガのリスクも伴います。
特に一般的な自宅の浴室には、段差があったり、石けんの使用などで滑りやすくなることもあり、介護の必要がない自立した高齢者の方でも思わぬ事故につながる可能性があります。
しかし浴室の環境を見直してちょっとした配慮や入浴時の介助を行うことで、安全で快適な入浴を楽しんでいただくことができます。
高齢者の入浴介助と注意点について、今回の内容をご参考にしてください。
目次
入浴介助とリラックス効果
ぬるめのお湯につかることで自律神経のうちの副交感神経が優位となり、さらに幸せホルモンとも呼ばれているセロトニンの分泌が促進され、心身ともにリラックスした状態となります。
また浮力がかかることで体重は9~10分の1ほどになるといわれており、身体を支える筋肉や関節への負荷が軽減して緊張がほぐれ、関節痛などが和らぐ効果も期待できます。
高齢者の入浴は半身浴がおすすめ
高齢者には半身浴が適していると考えられています。
体調の急変を予防するという観点では、湯温は38~40℃程度のぬるめのお湯で5分程度、長くても10分を目安にして長湯は控えるのが好ましいといわれています。
冬季には寒く感じない程度に少し湯温を上げ、湯量も胸あたりまで増やして温まるのもよいですが、首まですっかりお湯につかると心臓や肺に負荷がかかることがあるため注意が必要です。
またぬるめの半身浴であっても入る前には足からかけ湯をして、湯船の出入りはゆっくりと行うようにしましょう。
高齢者の入浴準備①事前の用意
入浴前に必要なものはそろえておきましょう。高齢者自身が入浴中に必要なものを取りに行くことは、急な体温変化やや血圧変化を招いたり、身体が濡れていることで足が滑ったりと事故のリスクが高くなります。
高齢者の入浴は介助が必要がない方であっても、ご家族が在宅していて、あまり夜遅くない時間に入浴するようにしましょう。
バスタオル
バスタオルは吸水性の良い、やわらかいものを用意して短時間で体が拭けるようにしましょう。
高齢者の皮膚は薄くなっているため、皮がむけやすいことがあります。
タオルで体を拭くときはこすらずに、ポンポンと軽くたたくようにしてタオルに水分を吸わせましょう。
オムツを含めた着替え
着替えの衣類と一緒に、オムツや尿取りパッドを使用している場合は忘れずに用意しておきましょう。
脱衣場にオムツや尿取りパッドをいくつか収納できる場所を作っておくと、オムツや尿取りパッドの使用に羞恥心を持つ高齢者の方でも用意しやすくなります。
ボディーソープ
固形石けんでも大丈夫ですが、固形石けんは水にぬれると滑って持ちにくく、扱いにくいことがあるので、ポンプ式のボディーソープの方が手軽です。
泡で出てくるタイプのボディーソープは泡立てる手間も省けて便利です。
スポンジ・ボディータオル
ご本人が使いやすいものと、介助者が使うものの両方を準備しておくと便利です。
高齢者の肌を傷つけないために、スポンジやボディタオルはやわらかく肌触りの良いものを使用しましょう。
入浴介助用品
入浴用のいす、浴槽用の手すり、入浴台、浴槽内のいすなど、入浴介助用品には他にもいろいろなものがありますが、上手に利用することで入浴時の事故を防止し、入浴する高齢者の方と介助する方、両方の負担を軽減することができます。
保湿剤やクリーム
保湿剤やクリーム、医師から処方されている軟膏などは入浴後の清潔な肌に塗りましょう。
処方されている軟膏などは医師の指示通りに使用し、乾燥を防ぐ目的の保湿剤はタオルで水分を拭きとったあと、できるだけ早く塗る方が効果的です。
背中や足の先など、ご自身で塗りにくい場所は介助者が塗りましょう。
高齢者の入浴準備②入浴補助用具
入浴補助用具とは、浴室の段差をなくしたり、浴室内での立ち上がりや座位を補助して、事故を防止するための補助用具です。
利用する方の身体機能に適した入浴補助用具を準備しましょう。
浴槽用手すり
浴槽用の手すりは、浴槽への出入りや浴槽内での座位を保持するための手すりです。
浴槽の縁にかけて取り付けるタイプは比較的簡単に取り付けられ、家庭用のさまざまな形状の浴槽に対応する商品があります。
壁に取り付けるタイプの手すりは工事が必要なものもありますが、介護保険の高齢者住宅改修費用助成制度が適用されます。
シャワーチェア
シャワーチェアは洗身のときに座る浴室用のいすです。
安定感があり、背もたれやひじ掛けの付いたもの、折りたたみできるものなどいろいろな種類があります。
座面がU字になっているものは、立ち上がることなく陰部を洗うことができます。浴室の広さや浴室への入り口の幅なども考慮してサイズを選ぶようにしましょう。
シャワーキャリー
シャワーキャリーは脱衣場や浴室で利用できる車いすです。シャワーチェアにタイヤがついたような形状で、シャワーキャリーに乗ったままシャワーを浴びることができます。
シャワーキャリーのタイヤは通常の車いすよりもタイヤが小さく、段差を乗り越えるのが難しいことがあります。浴室までに段差がある場合は段差を解消しておく方が利用しやすいでしょう。
滑り止めマット
脱衣場、浴室の床に敷いておくことで滑りにくくなります。
また浴槽の中に敷いておくと、お尻が滑るのを防いで座位が安定します。
色やサイズもいろいろあるので、使用場所に合ったものを選びましょう。
バスボード
浴槽の縁が高かったり、浴槽の縁をまたいで浴槽に入ることが難しい場合に、安全に浴槽に入るために利用します。
使い方は浴槽の両側の縁にバスボードを渡し、バスボードにいったん腰かけてから片足ずつ浴槽の中に入れます。
両足が浴槽内に入ったら手すりなどをつかんで浴槽内で立ち上がり、バスボードを外してゆっくりと座ってお湯につかります。
バスボードは浴室や浴槽のサイズに合ったものを使用しましょう。ぐらついているとかえって危険なことがあります。
また入浴中に取り外しをするので、軽くて持ちやすいものを選ぶとよいでしょう。
浴槽内でしゃがんだり、立ち上がる動作が必要なため、浴槽用の手すりや滑り止めマットを併用することでより安全性が高まります。
入浴介助用ベルト
立ち上がる際にバランスを崩すことがある方の入浴介助に使用するベルトです。
入浴する方の腰に巻いて固定し、介助者がベルトの持ち手を持って腰を浮かせることで立ち上がりや移乗を補助します。
素肌に巻いても負担の少ない素材で、着脱も簡単な仕様になっています。
同時に介助者が装着するベルトもありますが、高齢者の身体機能によって必ず使用するものではなく、介助者のベルトの持ち手を高齢者に持ってもらうことでより立ち上がりやすく安定感が増すため、併用すると効果的なケースもあります。
入浴介助の具体的な手順
入浴時にどのような介助が必要かは心身の状態によって異なりますが、適切な順序で入浴介助を行うことで、安全で快適な入浴時間を過ごしていただけます。
入浴前、入浴中、入浴後に分けて、高齢者が入浴する際の一般的な注意とポイントを挙げます。
入浴前に確認すること
入浴は空腹時や食事の直後は避けましょう。トイレを済ませ、水分補給をしてから浴室へ移動しましょう。
体の状態をチェック
顔色や皮膚など全身状態を観察し、変化がないか確認しましょう。
持病があったり、いつもと異なる様子があったときは、体温や血圧など実際に測定して確認しましょう。
食欲や睡眠の状態についても把握し、いつもと様子が異なるときには無理せず、足浴や手浴、蒸しタオルなどで全身を清拭するなど、別の方法を検討しましょう。
脱衣室と浴室を温めてヒートショックを防止
急激な温度変化によって血圧が大きく変動し、身体にダメージを及ぼすことを「ヒートショック」といいます。
特に冬場の寒い時期、暖かい部屋から寒い浴室へ移動することでヒートショックのリスクが高まります。
寒い時期には浴室暖房を使用したり、脱衣場に小型の暖房器具などを置いて、あらかじめ温めておくようにしましょう。
転倒をしないようにサポートする
着替えの際に、バランスを崩して転倒する可能性があります。特にセーターやTシャツなどかぶって着脱する衣類は、一時的に視界が遮られ腕を大きく動かすため、立位が不安定になることがあります。
脱衣場にもいすを置き、座って着替えると安心です。脱衣場から浴室に入る際には手すりにつかまっていただき、歩行機能に応じて、もう片方の手を支えるようにしましょう。
入浴中に注意すること
入浴中も表情や皮膚状態などを注意して観察しましょう。
介助者が浴室に入って介助をしない場合でも、脱衣場など声や音が聞こえる場所に待機していると安心です。
お湯は足元からかける
給湯と湯船の温度は、初めに介助者が実際に触って確認しておきましょう。
お湯をかける前には必ず声をかけ、心臓から遠い足先からお湯をかけます。
初めは少しずつお湯をかけながら、適温かどうかを確認しましょう。
入浴時間は10分程度と短めにする
入浴時間は10分程度を目安に、短めにしましょう。
急ぐ必要もありませんが、長時間の入浴はのぼせたり、めまいの原因となることがあり、転倒リスクや溺死のリスクも生じます。
特に暑い季節には熱中症や脱水症状にもつながりかねないため、注意が必要です。
熱いお湯に入ることは避ける
高齢者の中には暑いお風呂を好む方もいらっしゃいますが、65歳以上では特に、高温で入浴したときの事故が多くなっています。
42℃以上の高温浴では入浴の初めに血圧が30~50も急上昇し、この時に脳出血のリスクがあるというデータもあります。
熱いお湯の入浴は避けるようにしましょう。
本人ができることは任せる
本人ができることは、できる限り自分で行ってもらいましょう。
そもそも入浴はプライベートな時間であり、入浴の介助に対して嫌悪感を持つ方も多いものです。
自尊心を尊重し、身体機能を維持するためにも、安全を確保したうえで、できない部分だけを介助するようにこころがけましょう。
入浴後の注意ポイント
高齢者の皮膚は乾燥しやすく、入浴後の皮膚は特にデリケートな状態になっていることがあります。
体を拭くときにはこすらず、速やかに保湿クリームなどで皮膚のケアをしましょう。
爪もやわらかくなっているので、入浴後は爪切りにも適しています。
転倒予防のために足の裏を拭く
足の裏が濡れたままでいると滑りやすいため、浴室から出たらすぐに足を拭きましょう。
足ふきマットを置く場合は、マット自体が滑らないように、裏面に滑り止めの付いたものを使うなどの対策が必要です。
めまいやふらつきによる転倒を防ぐためにも、脱衣場にいすを用意し、いったん座ってからタオルで体の水分を拭きとり、着替える方が安心です。
しっかりと水分補給を行う
短時間の入浴であっても体の水分が失われ、脱水症状を引き起こす可能性があります。着替えが済んだら、水分補給をしっかりとしておきましょう。
特に暑い季節には、入浴後の水分補給に経口補水液を利用するのも効果的です。
体調をチェックする
入浴は高齢者にとって体力を使う行為のひとつであり、疲労を感じる方もいます。入浴後も表情や全身の様子を観察しましょう。
いつもと異なる様子があったり持病のある方は、実際に血圧や脈拍数などを計測し、異常がないことを確認しましょう。
高齢者が入浴をしないとどうなる?
人の皮膚には常在菌が存在し、その多くは肌の状態を良好に保つために役立っていますが、中には有害な細菌も存在します。
長期間入浴しないことで有害な細菌が増殖し、皮膚疾患や感染症を引き起こす可能性があります。
さらに臭いが出てくることで他者とのかかわりにも支障が生じます。
入浴の介助に拒否がある場合はその理由を探り、たとえ身近な家族でも同性の家族が介助を行うなどの配慮をしてみましょう。
自宅で入浴が困難な場合には、デイサービスなどを利用して入浴介助を受ける方法もあります。
拒否が強く入浴が困難な場合には、足や陰部だけシャワーで流したり清拭するなど無理のない代替方法を検討し、少しずつ試してみましょう。
高齢者の入浴介助のまとめ
入浴は高齢者にとって楽しみであるだけではなく、身体の清潔や皮膚状態を良好に保ち、温熱や水圧の効果によって新陳代謝の促進や運動効果による健康維持が期待できます。
しかしその一方でヒートショックや転倒など、急激な体調変化や事故のリスクも伴います。
高齢者の自尊心に配慮しながら、入浴補助用具なども利用した適切な入浴介助を行って危険を回避し、高齢者の方に安全で健康的な入浴時間を楽しんでいただきましょう。
 まごころ弁当
まごころ弁当 配食のふれ愛
配食のふれ愛 宅食ライフ
宅食ライフ すくすく弁当
すくすく弁当 まごころケア食
まごころケア食 ライフミール
ライフミール わけありなおかず屋さん
わけありなおかず屋さん 運営会社
運営会社 こだわりシェフ
こだわりシェフ おてがるシェフ
おてがるシェフ ラクゴハン
ラクゴハン ラクミール
ラクミール まごころ食材
まごころ食材 楽らく弁当
楽らく弁当
 HOME
HOME まごころ弁当とは
まごころ弁当とは 店舗検索
店舗検索 注文方法
注文方法 コラム
コラム お問い合わせ
お問い合わせ