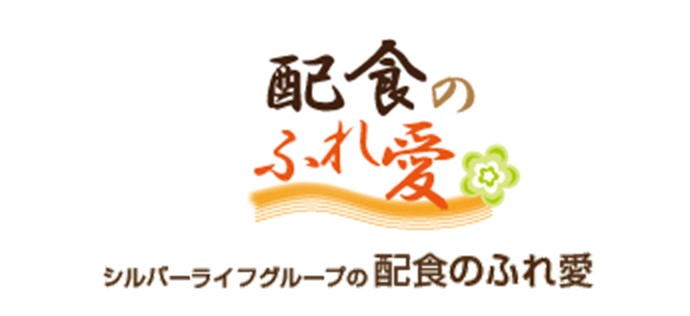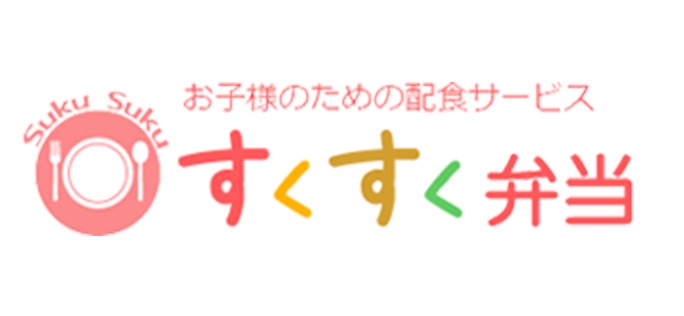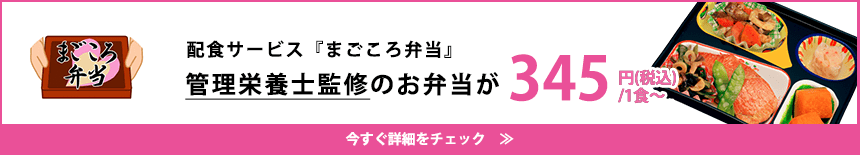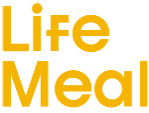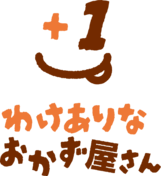寝たきりの高齢者の介護方法と介護疲れの軽減方法をすべて解説
作成日:2022年9月26日

「寝たきり」とは、何らかの原因で寝ている状態が6か月以上継続し、基本的に1日中寝たままで過ごしている状態を指します。
寝たきりになった方は自分で体を動かすことが難しいため、生活の全般において介助が必要であり、介護にも特別な配慮や工夫が必要なことがあります。
在宅で寝たきりの方を介護するための方法やポイントなどについて紹介します。
目次
介護のポイント~寝たきりの高齢者~
寝たきりの状態は身体機能が低下するだけではなく、内臓の機能や精神面にも影響を及ぼします。
また自力で体を動かすことが困難なため、介助の際に協力動作を得ることが難しく、介護者の負担も大きくなります。
寝たきりの高齢者の食事介助
寝たきりの方はほとんど終日をベッド(布団)上で過ごすため、何をするときにも周囲の環境が変わりません。
食事時には献立内容を伝えたり、食事のにおいをかいでいただくなど、食事に意識を向けることで食欲が増したり、誤嚥や窒息のリスクを低減することにもつながります。
食事前の準備
寝たきりの方は常に横になっているため、ウトウトとした傾眠傾向にあることが少なくありません。
食事前には声をかけて食事の時間であることを伝え、覚醒を促しましょう。上半身をできる限り起こし、クッションなどを利用して安定した座位が保持できるように整えます。
膝や足首を曲げることが可能な場合は膝を立て、足首を可能な限り直角に曲げた状態で足の裏に丸めた毛布や大きめのクッションなどを置いて足を支えると、お尻の位置が安定して座位が保持しやすくなります。
衣類や寝具が汚れないようにエプロンを着けたり、タオルやティッシュペーパーなどを用意しましょう。
おしぼりなどで手指を清拭し、歯ブラシや口腔ケア用スポンジなどで口腔ケアをします。
可能であればブクブクうがいもして、義歯がある場合は義歯を洗浄してから装着しましょう。
食事中の介助方法
食事介助のときは、食べる方の横に座ります。麻痺がある場合は麻痺のない側に座るのが基本です。
自分で口に運べる場合は、持ちやすい食具を使用して、手の届きやすい位置に食器を配置します。
介助で口に運ぶ場合は、食べる方に合ったひと口量を、ご本人のペースに合わせて運び、飲み込みを確認しながら進めます。
主食、おかず、水分を交互に口に運び、液体にむせ込みがある場合にはとろみをつけたり、ゼリーやペーストにするなど食事形態の調整をしましょう。
食後のケア
食事が終わったら口腔ケアをします。義歯がある場合は義歯を外して洗浄し、可能であればブクブクうがいをしましょう。
食べたものが逆流するのを防ぐため、食後はすぐに横にならず、しばらくは座位を保持します。
1時間を目安に、ご本人に苦痛が無いように座位を整えましょう。
寝たきりの床ずれを防ぐ方法
自分で体を動かすことができる人は、寝ている間も無意識に体を動かしたり寝返りをうっています。
しかし寝たきりの方は自力で体を動かすことが困難なため、介助で定期的に体位変換をしないと床ずれが発生します。
寝たきりの方の場合は床ずれができると治りにくかったり、悪化しやすい傾向があるので、床ずれを作らないようにすることが重要です。
床ずれとは
床ずれは「褥瘡(じょくそう)」とも呼ばれ、皮膚の同じ部分が継続して圧迫されることで生じます。
圧迫によって皮膚や皮下組織、筋肉への血流が悪くなり、十分な酸素や栄養が届かなくなることで、皮膚の赤みや内出血、水疱などの症状が現れます。
皮膚の圧迫に加えて、皮膚の乾燥、汗や尿による湿潤や汚れ、皮膚の摩擦やずれ、持病や栄養状態の不良などの条件によって発生しやすくなったり、治りにくくなることがあります。
悪化すると症状は皮膚の深部におよび、皮下脂肪や骨にまで広がることがあり、感染のリスクも高く治癒まで長期間がかかることもあります。
床ずれの予防
床ずれを予防するためには、同じ部分に継続して圧力がかからないようにすることが必要です。
特にかかとや仙骨、肩甲骨、腸骨、大転子部など骨が突出している部分には圧力が集中しやすいため、定期的に体位変換をしたり、クッションなどを使用して突出部位が圧迫されないような工夫が必要です。
体位変換は同じ姿勢が続かないように、仰向けや横向きが交互になるように体の向きを変えましょう。
体位変換の目安は2時間ごとといわれていますが、生活のリズムに合わせて実施しましょう。
体圧を分散させるマットレスなどを使用するのも、床ずれの予防に効果的なことがあります。
レンタルできることもあるので、担当のケアマネジャーなどに相談してみましょう。
床ずれができてしまったときのケア
軽症の場合は、定時での体位変換を行って患部を除圧し、洗浄して清潔を保ちましょう。必要に応じて医療機関を受診して軟膏などの処方を受けます。
床ずれが進行すると感染を伴ったり壊死組織を生じることがあります。
壊死組織がある場合は壊死組織を取り除く処置が必要なことがあるので、医療機関を受診したり訪問看護師による医療的処置を受けましょう。
除圧と清潔の保持は軽症の場合と同様ですが、感染の兆候がある場合には抗菌薬が処方されることがあるので、指示通りに使用します。
栄養状態が悪いと治癒しにくいことがあるため、十分なエネルギーとタンパク質、亜鉛やビタミンCなどの栄養素を十分に摂れることが理想的です。
食事だけで補うのが難しい場合には栄養補助食品などを利用すると、効率よく栄養摂取ができます。
寝たきりの高齢者の洗髪方法
寝たきりの方は入浴が困難となるため、洗髪も頻繁にはできないのが現状です。
清潔の保持はもちろん、さっぱりとして気分転換になるので、週に1回程度は洗髪できるのが理想的です。
①ビニールシートの上にバスタオルを敷き、その上に上半身をのせるように仰向けに寝ていただきます。首の下にまくらや畳んだバスタオルなどを置いて首を高くし、後頭部の下に洗面器を置きます。姿勢がつらい場合は肩の下にもクッションなどをあて、できるだけ安楽な姿勢に調整しましょう。
②バケツなどにお湯を汲んでおき、ペットボトルやじょうろを使って静かに髪をぬらしてからシャンプーで洗います。
③ペットボトルやじょうろを使って泡を洗い流します。初めに泡を取り除いてからすすぐと、少ないお湯で流すことができます。
④髪の水分をしぼり、タオルで包み込むようにして拭きとってからドライヤーでしっかりと乾かしましょう。
洗髪の注意点
洗髪を始める前に、使うものを全て準備しましょう。寝たきりの方にとって、洗髪のときの姿勢がつらいこともあるので、できるだけ短時間で手際よく仕上げるようにしましょう。
季節によっては洗髪後に体が冷えてしまうことがあります。洗髪を始める前に部屋の温度とお湯の温度を確認してから始めましょう。
耳にお湯が入らないように、イヤーキャップなどがあると便利です。
ドライヤーをかけるときは、頭皮や耳が熱くならないよう頭から離して乾かしましょう。
寝たきりの高齢者の清拭方法
清拭は上半身→下半身→陰部の順で、末梢から心臓に向かって拭いていきます。
顔から首、手から腕、胸、腹部、背中の順で拭き、女性は乳房の下もよく拭きましょう。
背中は横向きに寝ていただいて拭き、下半身は仰向けになって膝を立て、足首から足のつけ根に向かって拭きます。
そのあと趾間や足の裏を拭き、最後に臀部と陰部を拭きます。
清拭とは
清拭は、温かいタオルなどで体を拭いて清潔にすることです。全身を拭く「全身清拭」と部分的に拭く「部分清拭」があります。
皮膚を清潔に保つだけではなく、血行を促進したり、気分がリラックスするなどの効果もあります。
清拭の注意点
タオルは数枚用意し、初めに温度を確認しましょう。
タオルの面を変えながら、常に清潔な面で拭くようにし、陰部は陰部専用のタオルを用意しましょう。
高齢者は皮膚が薄くなっているため、強くこすらないよう注意が必要です。拭いた後は冷えることがあるので室温に配慮し、バスタオルをかけるなどして保温しましょう。
顔や手指、陰部など、ご自身で拭くことができる場合はご自身に拭いていただき、拭きながら皮膚の状態や爪、外傷がないかなど観察しましょう。
寝たきりの高齢者の排泄ケア
排泄ケアには身体機能に応じていくつかの方法がありますが、ご本人の排泄パターンをつかみ、毎日決まったタイミングで排泄できるようにしましょう。
加齢や疾患の影響で、尿意や便意を感じにくくなることがありますが、定期的な排泄ケアによって失敗を減らすことができます。
排泄ケアとは?
排便、排尿にかかわる支援が排泄ケアです。
トイレに座ることができる場合は、可能な限りトイレに移動していただくのが理想的ですが、寝たきりの方にとっては体力的に負担になる可能性もあるため、ご本人が納得する方法でケアするようにしましょう。
排泄方法の種類と選び方
① トイレを利用する
トイレまで移動することができ、ズボンや下着を上げ下げする間手すりにつかまって立てて、さらに排泄の間、便座に安定して座っていることができる場合に可能な方法です。
ご本人の身体機能だけではなく、トイレまでの移動方法やトイレの形状や広さによっても利用が難しい場合があります。
② ポータブルトイレを利用する
トイレまで移動することが難しい場合は、部屋にポータブルトイレを設置する方法があります。
移動時間なくすぐに利用できるので、失禁や転倒のリスクを低減できます。
使用中はパーテションを立てるなどプライバシーに配慮し、使用後はできるだけ早く排泄物を処理しましょう。
③ 尿器を利用する
ベッドから起き上がることが難しい場合は尿器を使用します。
男性用と女性用では尿器の形状が異なり、男性は仰向けか横向き、女性は仰向けに寝た状態で使用します。
布団を汚さないように腰から臀部にタオルを敷き、排せつ中は陰部にタオルをかけるなどの配慮をしましょう。
④ オムツを利用する
尿意や便意がなくなったり、尿意や便意を伝えることが困難となったときに使用する、排泄ケアの中では最後の方法といえます。
排泄ケアの注意点
排泄ケアは必要不可欠ですが、デリケートなケアなので配慮が必要です。排泄の方法にかかわらずご本人の尊厳を守り、快適な排泄ができるようにしましょう。
また夜間の排泄は、ご本人にも介護者にもストレスとなることがあります。
就寝前には排泄介助を済ませ、ご本人の排泄パターンに合わせた適切な方法で排泄ケアを行いましょう。
介護疲れを軽減させる方法について
これまでに挙げた介護は日常的な生活に伴うものであり、適切な方法で行わないと、介助する人もされる人にも負担になります。
さらに寝たきりの方の介護は昼夜を問わず必要であったり、意思の疎通が難しいケースも多く、介護者は心身ともにストレスを抱えることがあります。
介護を家族で分担したり介護サービスを利用するなど、介護疲れを軽減する方法をみつけましょう。
誰にでもある介護疲れ
寝たきりの方の在宅介護は、マンツーマンのつきっきりの介護となりがちです。
どんなに大切な人であっても、休みのない介護で疲労がたまることは当然のことなので、全ての介護をひとりでやろうと思わないようにしましょう。
訪問介護を利用する
訪問介護は訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問して、食事や入浴、排せつなどの身体介護や調理、洗濯、掃除などの生活援助を行う介護サービスです。
受けられるサービスの内容や自己負担額は介護度などによっても異なるので、担当のケアマネジャーなどに相談してみましょう。
訪問入浴介護を利用する
訪問入浴は看護師を含めた専門のスタッフが自宅を訪問し、専用の浴槽設備を使って入浴を介助するサービスです。
専用の設備を持ち込んで入浴ができるため、寝たきりの方でも湯船に入ることができます。
また看護師が同行しているため、健康面でも安心して任せることができます。
訪問看護を利用する
医療的ケアが必要な方に対して看護師などが自宅を訪問し、主治医の指示に従って処置や看護をするサービスです。
床ずれのケアでは薬や医療処置が必要なケースがあるため、訪問看護を利用すると適切なケアを受けることができます。
施設利用を検討する
寝たきりの方の状態によっては、在宅よりも設備の整った施設での介護の方が適しているケースもあります。
施設の入所には抵抗がある場合でも、ショートステイやデイサービスの利用などによって、在宅では負担の大きい介護を専門職によって受けることができます。
兄弟や親戚を頼る
マンツーマンの介護で介護疲れが限界に達してしまう前に、身近な家族や親せきを頼ってみましょう。
数時間、誰かに交代してもらって外出するだけでも、気分転換になります。
介護サービスを利用しましょう
寝たきりの方の在宅介護は、多くの場合で終日休みなく続きます。体力的な負担はもちろん、家の中で行うマンツーマンの介護は精神的にも大きなストレスとなります。
在宅介護で介護者が疲弊することは、介護される方にとっても幸せなことではありません。
疲れ切ってしまう前にケアマネジャーなど介護のプロに相談し、適切な介護サービスを利用しましょう。
 まごころ弁当
まごころ弁当 配食のふれ愛
配食のふれ愛 宅食ライフ
宅食ライフ すくすく弁当
すくすく弁当 まごころケア食
まごころケア食 ライフミール
ライフミール わけありなおかず屋さん
わけありなおかず屋さん 運営会社
運営会社 こだわりシェフ
こだわりシェフ おてがるシェフ
おてがるシェフ ラクゴハン
ラクゴハン ラクミール
ラクミール まごころ食材
まごころ食材 楽らく弁当
楽らく弁当
 HOME
HOME まごころ弁当とは
まごころ弁当とは 店舗検索
店舗検索 注文方法
注文方法 コラム
コラム お問い合わせ
お問い合わせ